再エネと水素が勝者へのカギ エネルギー革命には、技術・制度・人の3つのイノベーションが必要
-
印刷
-
共有
-
日本ビジネス出版は8月31日、『グローバル潮流から見る日本のカーボンニュートラル』をテーマに、オンラインによる環境ビジネスフォーラムを開催した。気候変動問題だけでなく、エネルギー安全保障や地政学リスクの点からも重要度を増す脱炭素への取り組み。トップバッターで登壇したICEF運営委員長の田中 伸男氏は、グローバルエネルギー危機の観点から、日本の脱炭素の在り方を説く。
エネルギー危機と環境危機 両軸への対応が迫られる
ロシアによるウクライナ侵攻に端を発した世界規模でのエネルギー危機により、世界各国でエネルギー・システム全体の見直しが迫られている。
歴史的なエネルギー危機で言えば、1973年、アラブ諸国が米国をはじめとする一部先進国に対し石油の禁輸をしたことでおこった石油ショックが思い浮かぶ。これにより、国際エネルギー機関(IEA)が発足。短期の石油危機に対する対応として戦略的備蓄によるエネルギー安全保障が図られた。
日本では、石油依存を減らし、石炭の効率的な使用や原子力の活用など、エネルギー源の多様化と同時に、中東だけに依存しない輸入国の多様化を図り、戦後のエネルギー戦略を進めてきた。
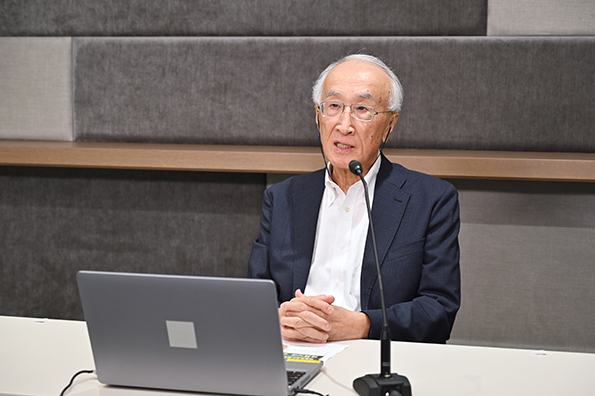
「前回の石油ショックは、『先進国へ中東の石油が来ない』という単純な絵でした。比べて今回は、先進国だけでなく、現在大量にエネルギーを必要とする新興国も含めた大きなクラッシュになったという世界的な広がりがあります」と田中氏。
さらに、ロシアから石油の供給が減るという石油ショックだけでなく、天然ガスがパイプラインで来なくなるガスショック、連動して電力価格が上がる電力ショック、足りない分を石炭でと各国が考えるため石炭の値段まで上がる。ありとあらゆるエネルギー源が足りなくなり値上がりするという意味で、史上初の大規模なグローバルでのエネルギー危機だと言える。
「石油だけでなく、ガス、石炭、電気、全てがクラッシュしたことに加え、地球環境問題も考える必要に迫られています。エネルギー危機と環境危機、両軸への対応を求められるという意味では、さらに深刻な危機状況にあると言えるでしょう」
2021年5月、IEAが『Net Zero by 2050』と題する報告書を発表し、世界的な注目を集めている。報告書では2050年にネットゼロを実現した世界からバックキャストし、その時までに世界のエネルギー需要構造がどうなっていくべきかを示している。
例えば、報告書の出た2021年時点からの新規の石油・ガス開発投資の停止、2035年時点での内燃機関自動車の新社販売禁止、2040年時点での世界全体での電力部門のゼロエミッション化実現など、センセーショナルな内容がマイルストーンで示された。
勝者の道へ、各国が舵を切る

「今回のエネルギー危機と地球環境危機の複合危機を受け、明らかに勝者と敗者が出て来ています」
戦費が増大する一方で、西側のマーケットを失い、民間投資が逃げ出し、若者の流出が進むロシアは、敗者と言える。REPowerEUで脱ロシアと脱炭素の同時達成を狙うEUは、炭素国境調整(CBAM)で世界標準を狙い、巨大なクリーン市場の力で勝者への道を進む。米国はインフレ対策法で国内産業の脱炭素化を後押しし、成功への道筋を描く。中国は、クリーンサプライチェーンを抑え、再エネのスーパーパワーとして再エネをベースとした経済により国の維持を図っている。
世界がエネルギー・システムの再構築へ向けそれぞれの舵を切るなか、日本が勝者となるためのカギとなるのが「再エネと水素」だと田中氏。
「日本は、石炭よりクリーンな液化天然ガス(LNG)を運ぶビジネスモデルを作って経済を発展させてきました。同じように、水素を何らかの形で安く運び、それによって発電することで、水素をベースにした経済を作る。一方で、世界中が取り組む再エネには、日本も取り組む必要があります。再エネをできるだけ大量に使い、安くしていく必要があります」
地球温暖化対策の鍵となるイノベーションを推進
世界的なエネルギー危機からの脱却と脱炭素を同時に実現するためのエネルギー変革にはイノベーションが欠かせない。
田中氏が運営委員長を務めるICEF(Innovation for Cool Earth Forum)は、地球温暖化対策の鍵となるイノベーションを推進するため、世界中の産官学リーダーが議論する知のプラットフォーム。

今年も10月4日-5日の2日間で開催予定だ。申し込みはこちら
「イノベーションには、まず技術のイノベーションがあります」
再エネ、グリーン水素、ブルー水素、バッテリー、小型原子力から大気中のCO2を直接回収するDAC(ダイレクトエアキャプチャー)まで。何が成功するか読めない今、あらゆる分野での技術革新に幅広く挑戦していく必要がある。
一方で、技術革新だけでは社会への実装、普及は進まない。「新たな技術を実装していくには様々な規制緩和、制度設計も必要です。可能になっていく技術イノベーションを実装していくための制度改革、すなわち政策のイノベーションも重要な要素となっていきます」
イノベーションの最後のポイントは買い手、需要家だ。例えば、Appleは、100%リニューアブルな部品を要求、メルセデスも2039年までのサプライチェーン全体でのリニューアブルにコミットしている。需要サイドがドライブする革命がいま、起こりつつある。
「最終需要家である消費者、人の行動がどう変わっていくか、人のイノベーションも、再エネ革命、グローバルなトランスフォーメーションを進めていく上では重要なテーマの1つだと思います」
ICEFでは、2023年10月4日、5日の2日間、10周年を記念したフォーラムを、ホテルニューオータニ東京で開催する。
『公正で安全かつ持続可能なグローバルGXのためのイノベーション』をテーマに、様々な国・地域からノーベル賞受賞者をはじめとした専門家が集まり議論を繰り広げる。ICEFでは、多様化がイノベーションの源泉であるとの認識から、ジェンダー平等と若手世代の参画を推進。
今回のフォーラムでは世界を舞台に各分野で活躍する数多くの女性がパネリストとして参加、また、次代を担う若手イノベーターのセッションも開催される。
「テクノロジーに対して懐疑的な見方をするSmil教授と『脱炭素2050の実現可能性』について議論する特別セッションも見どころの1つで、大変面白いディスカッションとなるかと思います」
また、技術セクターごとの議論では〈核融合〉にもフォーカスする。
「核融合については、政府の行う大規模なものから、小型の商業核融合まで様々あります。どれが成功するかは私も分かりませんが、1つでも成功すれば『エネルギー革命』が起こります。世界中で核融合に対する注目が高まるなか、テーマとして取り上げ、議論を深めたいと思います」
 ICEF事務局 問い合わせ先
ICEF事務局 問い合わせ先
email:icef2023-cs@icef.go.jp

