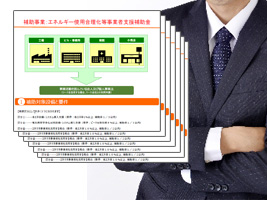失注を防ぐ! 省エネ補助金営業7つのポイント(2ページ目)
-
印刷
-
共有
-
4. 補助率1/2の申請(エネマネ事業者と連携)をする際、事業費は2000万円以上
エネ合補助金の場合は、エネマネ事業者と連携すると補助率は1/2となるが、金額的メリットを受けやすいボーダーラインが、補助対象となる経費が2000万円以上あるかどうかである。
例えば補助対象となる経費が1500万円で、1/3の補助率だと持ち出しは1000万円となる。ここで約500万円のEMSをつけて提案すると、2000万円になるが1/2の補助率となり、こちらも持ち出しが1000万円となる。そのため同じ持ち出し額でもEMSが活用でき、より高い省エネ効果が期待できる。
エネマネ事業者活用・活用なしの比較
| 補助対象経費 | 補助率 | 補助金額 | 持ち出し額 |
|---|---|---|---|
| 1500万円 | 1/3 | 500万円 | 1000万円 |
| 2000万円(1500万+500万<EMS導入費>) | 1/2 | 1000万円 | 1000万円 |
エネマネ事業者と連携する際はこの2000万円を基準として提案することが望ましいが、前もってエネマネ事業者と相談できるよう関係を作っておくことが必要だ。
5. 債務超過の場合、審査対象となるのは難しい
一方で、補助金申請の際は直近3年分の決算書を提出する必要があるが、債務超過の状態だとそもそも審査ベースにのるのは難しいという。
「債務超過だと審査が非常に厳しいですが、赤字の内容によっては採択の可能性があります」。(内田氏)
営業時に重要なのは経営層の理解
省エネ補助金営業が上手くいくポイントとして、内田氏は「担当者レベルだけでなく、経営層まで補助金活用して設備更新を行うことの理解が得られているかどうかがポイントです」と話す。
実際、担当者レベルだけで進めてしまい、採択されたにも関わらず社内の稟議が通らず実施できないというケースもあるという。採択された案件をキャンセルしてしまうと、二度と補助金採択されなくなってしまう恐れもあるので注意が必要だ。
営業マンにとって補助金活用は営業する際のセールストークとなる。より効果的なトークはどのようなものか。
「とくにエネ合補助金は年々採択率が下がっています。2014年度は約60%、2015年は約40%でした。近いうちに、設備更新を検討されているのであればできるだけ早く申請を行った方がよいです」と内田氏は解説する。提案時には採択率は毎年下がっているからこそ、早く申請した方がよいという話をトークに入れると効果的だ。
エネルギー使用合理化事業者支援事業 過去採択率
| 実施年月 | 申請数 | 採択数 | 採択率 | |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 1・2次 | 368件 | 293件 | 79.6% |
| 平成24年度 | 1・2・3次 | 1197件 | 907件 | 75.8% |
| 平成25年度 | 1次(5月) | 3802件 | 1394件 | 36.7% |
| 平成26年度 | 1次(6月) | 2400件 | 1472件 | 61.3% |
| 平成26年度 | 補正(3月) | 1822件 | 449件 | 24.6% |
| 平成27年度 | 1次 | 3322件 | 1332件 | 40.1% |
エネ合補助金は年々ハードルが上がっている ※リミックスポイント調べ
申請経験者をサポートすることがポイント
よく断り文句で聞くのは「申請は面倒だから、もう2度やりたくない」というケース。逆にこのようなケースこそ、補助金申請のサポートを必要としているという。
「実はエネマネ事業者と連携した申請方法だと1/2の補助額がつくことはあまり認知されていません。さらに、エネマ事業者と連携すると申請のやり取りがとてもスムーズになるため、申請の手間が大きく省けるのです。我々の場合、申請をサポートさせて頂くことも多いので、これまでの実績についてお話するだけでも、メリットを感じて頂くことも多いです」。
1/2の補助額は顧客にとっても非常にメリットが多いため、エネマネ事業者と連携して提案できる体制を作ることが重要だ。年々採択が厳しくなっている省エネ補助金だが、補助金の特性と顧客の情報をしっかりと把握することで、顧客をサポートする提案は可能になる。
★省エネ補助金の基本が押さえられる資料を下記からダウンロードできます。
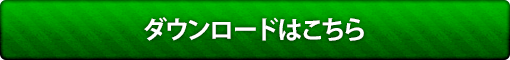
 株式会社リミックスポイント(マザーズ上場)
株式会社リミックスポイント(マザーズ上場)2016年度 設備導入支援特設ページ公開中
- 1
- 2