エネルギー会社が仕掛ける新たなまちづくり
-
印刷
-
共有
-
「まちづくり」はSDGsのなかでも大きなテーマだ。そして人々の暮らしに欠かせない「エネルギー」をいかに生み出すべきかは、重要な課題である。
自治体との協働で電力供給を行うLooopの小嶋氏(取締役 電力事業本部 本部長)、国のエネルギー政策に関わってきた東工大柏木教授、全学でのSDGs推進事業に従事する岡山大横井副学長が、2019年6月13~15日まで大阪で開催された「SDGs未来会議」にて、「官民協力で実現する『持続可能なまちづくり』— エネルギーから考える地域課題の解決 — 」をテーマに開催されたパネルディスカッションに登壇。これからのまちづくりのあり方と、それを支えるエネルギーの未来を語った(モデレーター 環境ビジネス 編集長 白田 範史)。
Looop社の取り組みなどを紹介した詳しい資料を公開しております。こちら、もしくは文末より資料ダウンロードできます。
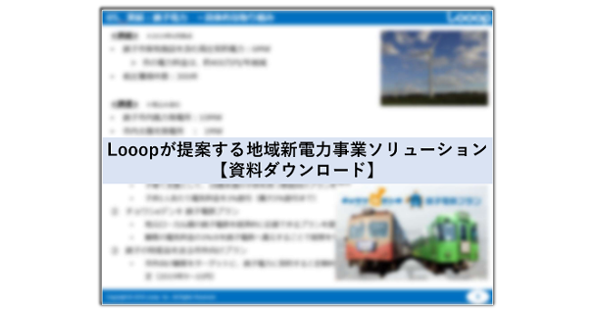
地域内で資金を循環させるしくみづくりが鍵

特命教授・名誉教授 柏木 孝夫 氏

副学長(海外戦略担当) 横井 篤文 氏

電力事業本部 本部長 小嶋 祐輔 氏
―SDGsゴール17にもあるように、パートナーシップは課題解決に欠かせません。
まずは、官民連携でまちづくりを進める際のポイントや、地域におけるSDGsのあり方について伺いたいと思います。
横井氏 地域における連携の難しさのひとつとして、組織や自治体間の壁があります。
しかし大学人として官民連携に取り組むうちに、各地の国立大学はニュートラルな存在で、官民をつなぐ要だと実感しました。大学は連携のプラットフォームになりうる存在として期待できるのではないでしょうか。
また、プロジェクトはシーズがないと進まないとも感じます。SDGsのアクションを起こすためには、169のターゲットまで掘り下げた議論が必要です。地域のシーズをどうターゲットに活用できるかが、連携推進に欠かせません。
―まちづくりにおいては、エネルギーの地産地消が注目されています。柏木先生がアドバイザーを務めておられる「真の地産地消型エネルギーシステムを構築する議員連盟」などの動きもありますね。
柏木氏 さまざまな検討がなされていますが、重要なのは『真の』の意味。エネルギーもお金も地域のなかで生まれて地域の外に流出しない、域内で富が回る地産地消のエネルギーシステムを意味します。
まちづくりでは、自治体が抱えるゴミ収集などの課題を核にすえ、産官学金(金融)言(マスコミ)が連携することが重要です。
―Looop社は、地域エネルギー会社である銚子電力を立ち上げました。
小嶋氏 銚子電力は昨年6月に、銚子市や地元金融機関の方々などとの協働で設立されました。連携では、地域で信頼感を持って受け入れてもらうこと、そのために、地域の課題に即した提案を行うことが必須です。
漁業が盛んな銚子市では、例えば大型冷凍倉庫など漁業関連施設での多量の電力使用が課題でしたが、私たちは解決に向けたノウハウを持っていました。弊社のサービスありきでなく地元起点のご提案ができたことが、連携推進に欠かせなかったと思います。
低下する再エネコストが、まちづくりを変える
―開発途上国と違い、日本では基本的にどこでも電気が使えます。こうした状況下でのまちづくりとエネルギー課題は何だとお考えでしょうか。
小嶋氏 電力は足りていますが、再エネの普及はまだ足りないと感じています。
日本でも、太陽光を中心とした再生可能エネルギー(再エネ)の発電コストは下がってきており、エネルギーの地産地消が可能となる土壌はできあがりつつあります。これまでの日本では、『遠くの発電所から大量の電気を運んでくる』のが常識でしたが、この認識が変わることも課題のひとつだと感じます。
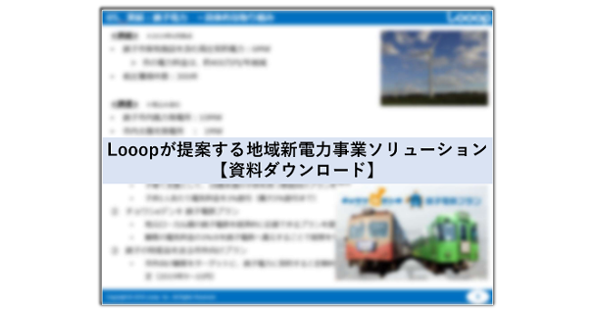
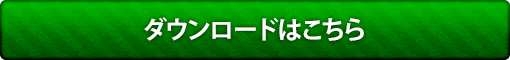
- 1
- 2

