北九州市、地域資源の循環でSDGs達成を目指す新プロジェクト始動(2ページ目)
-
印刷
-
共有
-
障がいのある方の雇用を作り出す
『紙の循環から始める地域共創プロジェクト』の目的は、〈紙循環システムの構築〉〈新たな雇用の創出〉〈将来世代人財育成の支援〉を通し、環境×経済×社会の価値共創とサーキュラー・エコノミーの実現を目指すことだ。
プロジェクトの特長は、(1)様々な企業や団体、学校等と『ペーパーラボ』の利用をシェアする(2)地元で排出された古紙をアップサイクルして再利用する(3)産学官民の連携がある(4)障がいのある方の参加がある、と大きく4つ。特に、古紙の回収や選別、アップサイクル品の加工といった部分で、障がいのある方の雇用を作り出していることは大きな特長と言える。障がい者雇用は簡単ではなく、一社で特例子会社を作るのはハードルが高く、取り組みたくてもなかなか進まない実情がある。
「『ペーパーラボ』には社会包摂性につながる活用事例があり、本プロジェクトでもそうした視点で課題解決に寄与できる仕組みができたらと考えていました」(網岡氏)
今回、プロジェクトに参加しているのは、障がいのある方の就労や自立訓練を支援する障がい福祉サービス事業所の運営を活動のひとつとしているNPO法人『わくわーく』。現在、18名ほどのスタッフが働いており、製鉄関係の下請け事業やお菓子づくりなどを行っている。

「わくわーく」のみなさん

NPO法人わくわーく理事長
プロジェクトの話を聞き、すぐに引き受けたという理事長の小橋 祐子氏。「私たちのような事業所では、働く人の賃金の低さが問題になっています。下請け事業やお菓子を作っても、それほど数をこなせるわけではなく、分配できる金額も少ないのが現状ですが、今回は環境に配慮したプロジェクトという面でも社会的意義が大きく、働く側の『やりがい』や『付加価値』を生み出す仕事だと感じました」と話す。
障がいのある方の携わる仕事というと、単純作業が多いイメージがあるが、今回のプロジェクトでは、古紙の回収にとどまらず、仕分けやアップサイクル品の加工など、仕事の幅が広がっていく。また、古紙の回収で企業や自治体、学校などを回り、地域との接触機会が増えることで、障がいのある方の雇用に対する理解が深まる効果もある。
乾式オフィス製紙機『ペーパーラボ』
プロジェクトの中核を担うエプソンの乾式オフィス製紙機『ペーパーラボ』は、オフィス等で発生した古紙を繊維化し、水を使わず(※)新たな紙を生産することで、地域全体で使用済み用紙を廃棄せずに再資源化。木材資源の100%節約、水消費量の99%削減、CO2排出量の34%削減など、環境負荷の低減に貢献する。
エプソン販売の多田 悠輝氏は「複数の企業や団体と一緒に『ペーパーラボ』を活用していくという発想自体が、これまでにない取り組みでした。ただ、こうしたプロジェクトを色々な企業や団体と取り組んでいく場合、実は『紙』は非常に分かりやすいアイテムだとも言えます」と話す。紙は老若男女問わず誰もが触れるものということが、今回のプロジェクトの根幹にある。
北九州市では、エコタウンの取り組みの中で、リサイクルコンビナートの構築を全国に先駆けて行ってきた。しかし、実際にリサイクルしている場面を、一般の人は見ることができない。
「今回のプロジェクトの大きな意義の1つは、オンサイト。すなわち自分の目の前で紙が再生されること、自分の身の周りでサイクルが回っていることを体感できることは、行動変容を促す上でとても大切な要素です」(網岡氏)
プロジェクトの数値目標としては、20団体以上のプロジェクト参加、10団体以上の古紙回収、もしくはアップサイクル品の購入サービス利用(2021年度以降)、2021年3月末までに15万枚のA4用紙の古紙回収、2022年3月までに40万枚のA4用紙古紙回収を定めている。
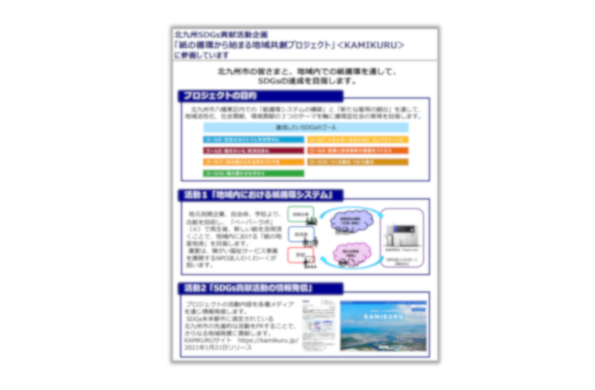 ダウンロードはこちら
ダウンロードはこちら
