脱炭素ビジネス法律基礎講座 温対法/省エネ法編
-
印刷
-
共有
-

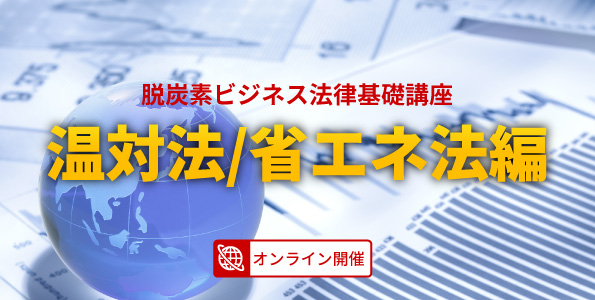
実務者はもちろん、脱炭素に関わるビジネスパーソンが知っておくべき基本的な法律を把握する!
社会は『脱炭素』へ大きく舵を切り、そして加速し続けています。
企業も脱炭素に向けてビジネス展開していく上で、温室効果ガスの排出抑制や省エネルギー化がより一層求められます。
地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「温対法」)とエネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「省エネ法」)では、温室効果ガス排出量の報告制度が定められています。 この2つの法律は、時代とともに改正を重ねています。
報告義務対象となる企業の実務担当者はもちろん、製品・サービス開発、営業など脱炭素に携わるビジネスパーソンは押さえておくべき基本的な法律です。
【温対法とは】
温対法は、1997年に京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)での京都議定書の採択を受け、日本の地球温暖化対策の第一歩として国、地方公共団体、事業者、国民が一体となって地球温暖化対策に取り組むための枠組みを定めたものです。
2006年4月1日から、温室効果ガスを多量に排出する特定排出者に自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられています。また2021年には改正温対法が成立し、「2050年カーボンニュートラル」が基本理念として明確に位置付けられています。
【省エネ法とは】
省エネ法は、石油危機を契機として1979年に制定されました。工場等、輸送、機械器具等についての省エネ化を進め、効率的に使用するための法律です(建築物についての規制は、2017年に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」)へ主要内容が移行されました。)。
工場・事業所のエネルギー管理の仕組みや、自動車の燃費基準や電気機器などの省エネ基準におけるトップランナー制度、需要家の電力ピーク対策などを定めている、日本の省エネ政策の根幹となる法律です。
本セミナーでは
・そもそも温対法・省エネ法はどのような法律?
・どの事業所が対象となるのか?
・対象事業者が実施することは何があるのか?
・温対法と省エネ法の違いとは?
・最近の改正ポイントは?
などのテーマを解説します。
また、本セミナーでは、温対法及び省エネ法の歴史、背景を理解し、企業が事業運営をしていく際の取組や留意点、実務者の実施事項などの基本を法律の視点から解説します。
※事業会社に向けたセミナーのため、法律事務所等の法律関係の方のお申込・ご参加はご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。
申込締切:2021年7月19日(月)
このような方におすすめです
- 脱炭素に関わる部署に異動になった。
- 社員教育の一環として新入社員を学ばせたい。
- なかなか法律を読む機会がない・時間が取れない。
- 基本的な法律は押さえておきたい。
プログラム
- ・法律がつくられた背景
- ・法律の内容・特徴、基本的な考え方
- ・これまでの改正の経緯
- ・温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度のポイント
- ・事業者が守るべきこと、ビジネスへの活用
- ・改正温対法で何が変わるか
- ・法律がつくられた背景
- ・法律の内容・特徴、基本的な考え方
- ・これまでの改正の経緯
- ・エネルギー使用状況等定期報告義務のポイント
- ・トップランナー制度
- ・事業者が守るべきこと、ビジネスへの活用
- ・建築物省エネ法との比較
◇まとめ
◇質疑応答
- 内容が一部変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 途中休憩あり。
- 本講座は、質疑応答時 講師と受講者 双方でコミュニケーションがとれます。
オンラインセミナー 注意点
【視聴について】
- ・本講義はオンライン配信にて実施をいたします。
- ・インターネット回線が安定した環境、PCでご受講できる環境をご用意ください。
- ・ヘッドセットやイヤホンでのご受講をおすすめいたします。
【受講上のご案内】
- ・講義はビデオ会議ツール(Zoom)での配信となります。
- ・ご利用されるPCなどへ事前にZoomのインストールが必要です。
- ・受講用URL、受講方法はセミナー事務局より3日前を目安にお送りさせていただきます。
- ※ご案内メールがシステムの都合届かない場合がございます。2日前までに届いていない場合はセミナー事務局までお問い合わせください。
【受講上の注意点】
- ・原則 LIVE配信となりますのでご注意ください。
- ・領収書はマイページよりダウンロードすることができます。
- ・本講義の講義資料および配信映像の録画、録音、撮影など複製ならびに二次利用は一切禁止です。
- 上記が確認された際は、弊社のサービスの利用停止と、法的措置をとらせていただく可能性があります。
講師
森・濱田松本法律事務所
弁護士
山崎 友莉子 氏
紛争案件、M&A案件、企業再生案件を含め、幅広くリーガルサービスを提供している。
2019年より慶應義塾大学大学院法務研究科及び慶應義塾大学の非常勤講師として「環境法と災害」「環境学入門」などの講義を担当。
現在は、電力分野を中心としたエネルギー分野に関する多数の案件に関与している。
申込締切:2021年7月19日(月)
| 日時 | 07/27(火) 10:30~12:30 (接続開始:10:15~) |
|---|---|
| 場所 | オンライン開催 |
| 主催 | 株式会社日本ビジネス出版 環境ビジネス編集企画部 |
| 共催 | |
| 定員 | 80名 |
| お問い合わせ先 |
株式会社 日本ビジネス出版 TEL: 03-5287-8600 (受付時間 9:00~18:00※) Mail:seminar@kankyo-business.jp ※9:00~18:00(土・日曜日、祝日を除く) |
| 価格 | 一般会員価格:13200円 |
1. 環境ビジネスオンライン
このプライバシーポリシーは、環境ビジネスオンライン(https://www.kankyo-business.jp/)を利用した情報提供サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供する株式会社日本ビジネス出版(以下、「当社」と総称します。)が、本サービスをご利用される皆様(以下、「利用者」といいます。)から取得する個人情報の取扱方針を定めるものです。
. サービス運営事業者
株式会社 日本ビジネス出版
. 管理者(若しくはその代理人)の氏名又は職名、所属及び連絡先
管理者名 : 白田 範史
所属部署 : 株式会社 日本ビジネス出版 環境ビジネス編集部
連絡先電話番号 : 03-5287-8600
4. 個人情報の取得
当社は、本サービスの提供に必要な範囲で、主に次のような場合に利用者に関する情報を取得します。
・本サービスを提供するウェブサイトへアクセスしていただく場合等
・本サービスへご登録いただく場合
・展示会、セミナー、その他イベントへのお申し込み、アンケートへのご協力、懸賞へのご応募をいただく場合
・本サービスに関して当社にお問い合わせをいただく場合
・サービス提供者/提携先が本サービスとは別に取得した個人情報が当社に提供される場合
・本サービスをご利用いただく場合
利用者が本サービスを提供するウェブサイトへアクセスした場合等は、利用者のブラウザーから、IPアドレス、クッキーやウェブビーコン等を利用して、利用者の広告やウェブサイトの閲覧履歴や閲覧状況、ご利用環境などの情報を自動的に取得します。
本サービスへご登録いただく場合、利用者の「氏名、メールアドレス、生年月日、性別、職業」等の個人情報をお伺いします。
また、ご登録後に本サービスを利用されますと、当社は、利用状況に関する以下のような情報を、利用者を識別できる情報と関連付けて取得します。
・本サービス内の各ページ・機能等へのアクセス履歴
・サービス・商品の利用・購入等の取引履歴個別のサービスへの登録状況
・展示会、セミナー、その他イベントへのお申込み、アンケートへのご協力、懸賞へのご応募の状況
また、当社は、サービス提供者/提携先から、利用者と当社やサービス提供者/提携先との間でなされた取引記録や決済に関する情報の提供を受ける場合があります。
5. 個人情報の利用目的
当社は、利用者から取得した個人情報を、次の目的に利用します。
(1)当社による本サービスの提供、および利用者による本サービスの利用のため
・本サービスを利用する際の、ログイン時またはログイン後の情報自動表示のため
・電子メール配信サービスのお申し込みの確認や各種メール送信のため
・契約の履行(商品、サービスの提供等)のため
・商品、サービスに関する情報の提供および提案のため
・商品、サービスの企画および利用等の調査に関する、お願い、連絡、回答のため
・商品、サービス、その他のお問い合わせ、依頼等の対応のため
・展示会、セミナー、その他イベントに関する案内、回答のため
・代金の請求、回収、支払い等の事務処理のため
・その他一般事務の連絡、お問い合わせ、回答のため
・ご要望いただいた広告掲載会社への資料請求等の仲介のため
・各種アフターサービスの提供のため
(2) 本サービスの改良、カスタマイズその他利便性向上のため
・サービス・商品等の内容の改善や新サービス・新商品の開発のため
・本サービスのご利用にあたってご覧いただくコンテンツや広告を、登録情報、利用状況等により、それぞれの利用者向けにカスタマイズするため
・利用者が注文したサービス・商品等に関する満足度等、本サービスに関する調査・アンケートのため
・本サービスのご利用にあたってご覧いただく、第三者から提供されるコンテンツや広告を利用者にとって利便性の高いものとするための、登録情報や利用状況の分析、または分析のためのアンケート対象の抽出、分析結果の第三者への提供のため(※当社が第三者に提供する分析結果に個人が特定されるような情報は含まれません)
・本サービス外での広告の配信状況の把握、広告効果の測定及び、行動ターゲティング広告の表示(一部サイトのみ)のため
(3)その他本サービスの提供のため
上記(1)および(2)に付随して必要な範囲で、当社による本サービスの提供のため
6. 個人情報の開示
利用者は、当社に対してご自身の個人情報の開示等(利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止または消去、第三者への提供の停止)に関して、当社問合わせ窓口に申し出ることができます。その際、当社は利用者ご本人を確認させていただいたうえで、合理的な期間内に対応いたします。
7. 個人情報の共同利用
当社は、以下の内容において、個人情報を共同利用することがあります。
・共同して利用される個人情報の項目:アカウント情報(氏名、性別、年齢、住所、所属組織、連絡先)、サイト内における行動履歴・デバイス情報・購入履歴、ネットワーク広告に関する情報、それらを基に生成される個人の興味関心に関する情報
・共同して利用する者の範囲:株式会社宣伝会議、学校法人先端教育機構
・共同して利用する者の利用目的:上記5.「個人情報の利用目的」のとおり
・個人情報の管理について責任を有する者:株式会社 日本ビジネス出版
8. 個人情報の第三者提供
当社は、以下のいずれかに該当する場合を除き、利用者本人の同意なく、個人情報を第三者へ開示または提供しません。なお、共同利用の場合および業務委託先への提供の場合は第三者への開示または提供にあたりません。
・商品の発送 、資料送付 、決済処理 を第三者に委託する場合
・電子メール配信などのサービスにおいて、第三者が提供するサービスを利用する場合
・展示会、セミナー、その他イベントを第三者と共催している場合
・個人情報保護法以外の他の法令に基づき、個人情報を第三者提供する場合
・統計情報など個人を直接特定できない情報として加工した状態で提供する場合
・利用者の申し込みに基づき、広告掲載会社へ問い合わせ・資料請求等を仲介する場合
・人の生命、身体又は財産の保護のために個人情報の第三者提供が必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
・国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
9. データ保存期間
当社は、本サービスの提供に必要な限り、利用者の個人情報を保持します。最後の利用・変更・アクセスののち3年を以って当該のデータを消去します。
10. 国外へのデータ移転
当社は、本サービスで収集した個人情報を別の国へ移転する場合があります。その場合、当社は当該情報移転に際し、法令が定める内容に従い、必要かつ適切な措置を講じます。
11. ご本人が容易に認識できない方法により個人情報を取得する場合について
クッキー(Cookies)は、利用者が当社のサイトに再度訪問した際、より便利に当サイトを閲覧していただくためのものであり、利用者のプライバシーを侵害するものではなく、また利用者のコンピューターへ悪影響を及ぼすことはありません。
また当社のサイトでは個人情報を入力していただく部分にはすべてSSL(Secure Sockets Layer)のデータ暗号化システムを利用しております。さらに、サイト内における情報の保護にもファイアウオールを設置するなどの方策を採っております。ただし、インターネット通信の性格上、セキュリティを完全に保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
12. お問合せ窓口
利用者の個人情報に関するお問合せにつきましては、下記窓口で受付けております。
〒107-8418 東京都港区南青山3-13-18 313南青山 6F
株式会社 日本ビジネス出版 個人情報お問い合わせ窓口担当宛
TEL:03-5287-8600 FAX:03-5287-8601
(受付時間 9:00~18:00※)
※土・日曜日、祝日、年末年始、ゴールデンウィーク期間は翌営業日以降の対応とさせていただきます。
13. 免責・注意事項
環境ビジネスオンラインのコンテンツ(※)は作成時点までの信頼できると思われる各種情報、データに基づいて作成されていますが、その正確性、相当性、完全性などに対して日本ビジネス出版(以下、当社)およびその情報提供者は責任を負いません。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません(※当社が承諾したうえで、ソーシャル・メディア上で配信・共有されたものを含みます)。
環境ビジネス オンラインのコンテンツは投資・購買勧誘を目的としたものではありません。利用者は環境ビジネス オンラインの各コンテンツより得た情報を、利用者ご自身の判断と責任において利用していただくものとします。
環境ビジネス オンラインのコンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社およびその情報提供者は責任を負いません。
環境ビジネス オンラインでは、サイト内で商品を購入できるようになっています。購入に際して利用者が万一損害を被った場合も当社は責任を負いません。購入に関するお問い合わせは各販売者へお願いします。
当社は、以下の場合に環境ビジネス オンラインのサービスの全部もしくは一部を中止することがあります。当社は、環境ビジネス オンラインの中止によって利用者が被った損害について、一切責任を負いません。
・システムの保守天災または第三者からの妨害行為などにより、サービス提供が困難と判断したとき
・その他やむを得ずシステムの停止が必要と判断したとき
当社は、電気通信事業者、データセンターなどの障害により、利用者が環境ビジネス オンラインのサービスの全部もしくは一部をご利用になれなかった場合に利用者が被った損害について、一切責任を負いません。
14. パソコン向けサービスの利用環境
環境ビジネス オンラインは以下の閲覧環境でのご利用を推奨しています。それ以外の環境の場合には、一部機能が使用できない可能性がございますのでご了承ください。
OS
・Windows 7以上
・Mac OS X 10以上
・Android OS 6以上
・Mac iOS 10以上
ブラウザー
・Internet Explorer 最新版
・Microsoft Edge 最新版
・Google Chrome 最新版
・FireFox 最新版
・Safari 最新版
設定
・JavaScriptが「有効」であること
・Cookieを受け入れる設定であること
環境ビジネス オンラインでは、一部のサービスでご利用者から個人情報をお預かりすることがありますが、その際にはSSLにより情報を暗号化することで通信を保護しています。SSL暗号化に対応したブラウザーをご利用ください。
※上記の環境での動作を基本的に確認していますが、お使いの環境によっては一部表示上の不具合が発生する可能性があります。
※通信環境、パソコンの性能によっては、快適にご覧いただけない場合があります。
15. EU域内情報提供者の権利
EU域内から個人情報を提供した利用者は、当社が保有する利用者の個人情報へのアクセス、訂正、消去、処理の制限、データポータビリティ、異議を唱える権利(以下「データ主体の権利」といいます。)を有します。利用者の個人情報に対する各種権利のご請求は、当社のお問い合わせフォームよりご連絡下さい。
