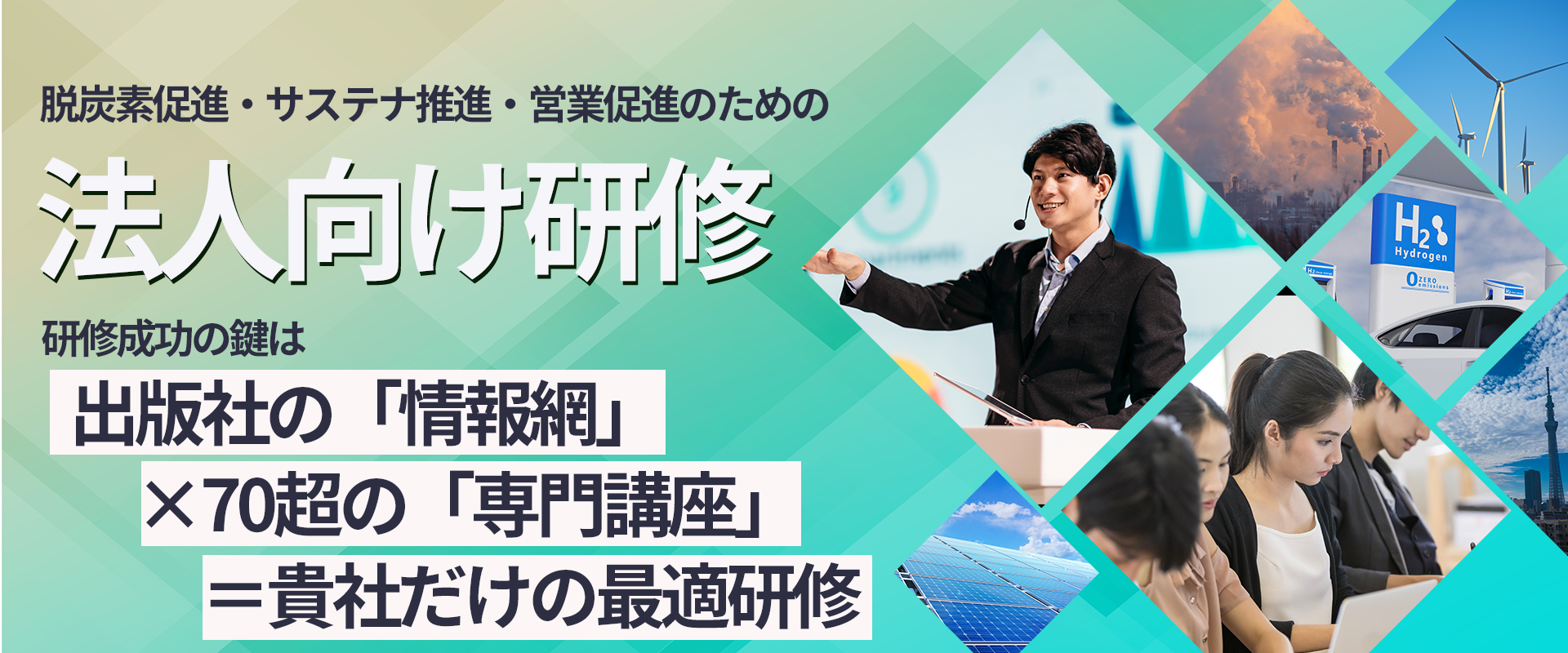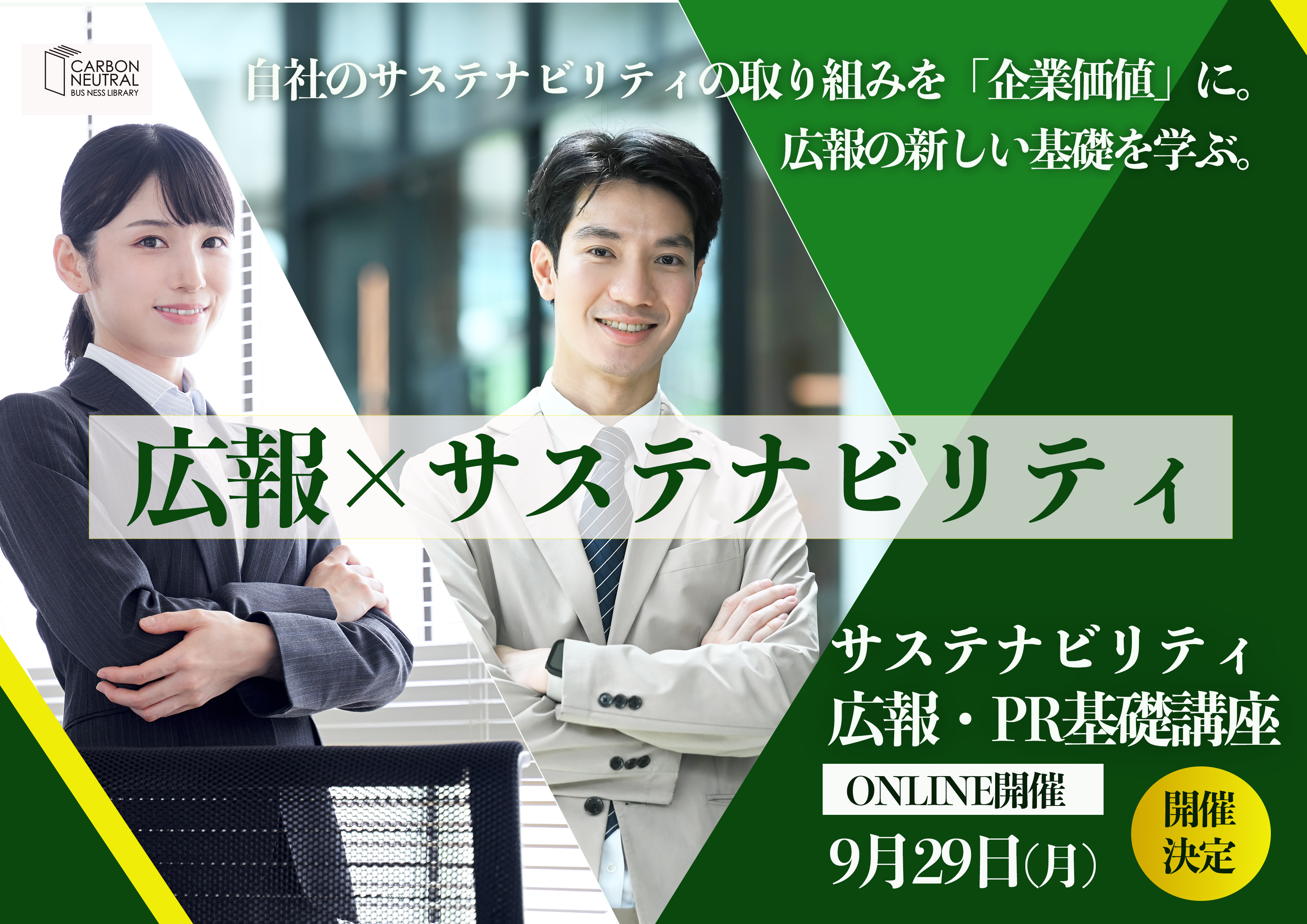環境用語集 REACH(化学物質規制)
REACH(化学物質規制)とは
電気機器や自動車などの工業製品は便利な生活や効率的な事業活動に欠かせないものですが、工業製品にはさまざまな化学物質が使われている。そのなかには、扱い方を間違うと人体や自然環境にマイナスの影響を及ぼすものも少なくない。
そこで、現在市場に流通しているものも含めて、化学物質をしっかりと管理しようと定められたのが、欧州議会の定めるREACH(リーチ)規制である。
REACHは、下記の通り、化学物質の包括的な管理体制の構築を目指している。
R:Registration(登録)
E:Evaluation(評価)
A:Authorisation and Restriction(承認と規制)
CH:Chemicals(化学物質)
既存の物質まで含めた幅広い規制
REACHが日本の「化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)」や アメリカ合衆国の「Toxic Substances Control Act」と大きく異なる点は、既存の物質を含めて全化学物質を対象とし、 必要なデータが登録されていない物質は、製造や供給ができなくなるという点だ。
REACHの条文の日本語訳は環境省が公表している。
2008年10月から改正に向けた審議が始まった日本の化審法の改正では、国内でもより幅広く化学物質を管理しようとする動きがみられ、REACHを意識した内容となる見込みだ。産業構造審議会、厚生科学審議会、中央環境審議会のそれぞれの下部組織で編成する 「化審法見直し合同委員会」によ2009年10月の会合に基づき、「2010年に向けた化審法の新体系」と題する報告書案をまとめた。
その後のパブリック・コメントの内容も踏まえ、化学物質審査規制法(化審法)改正案を2009年の通常国会に提出し、2010年度から導入される予定だ。
その内容の骨子によると、
- 現在、届け出義務のある化学物質約1000種を約2万種のすべての化学物質に拡大する。
- 一定量以上の化学物質を製造・輸入する企業に対し、製造・輸入量や用途を記録し、毎年度末に報告する義務を課す。
- 環境中への排出が多いものや、長期的な安全性などが確認されていない物質を「優先評価化学物質」に指定し、さらに詳細な安全性評価を求める。
この法改正により、報告が義務づけられる企業は、化学メーカーや商社、自動車、電機など大幅に増える見込みだ。 手続きなどで新たにかかる費用は総額40億円と見込まれているとのこと(2020年まで)。
化審法改正の背景
2002年8月26日から9月4日まで、南アフリカ共和国のヨハネスブルグで国際連合により開催された「地球環境問題に関する国際会議」(World Summit on Sustainable Development :WSSD)で、化学物質管理に関する世界共通の中長期的目標として、「2020年までに、全ての化学物質を健康や環境への影響を最小化する方法で生産・消費する」ことが決議された。その具体的な行動計画として「国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ」(Strategic Approach to International Chemicals Management:SAICM)がまとめられ、 2006年の国連環境計画(UNEP)において承認されている。
化審法改正はこの合意を受けたもので、EUのREACH規制は、日本の化審法に先立って実施に向けて動き出したということになる。
世界で始めてのITが不可欠の法律
2006年12月13日EC規則 No 1907/2006として可決
2007年6月1日より実施
すべての生産者・輸入者は、生産品・輸入品の全化学物質(1トン/年 以上)の、人類・地球環境への影響についての調査結果を、欧州化学物質庁(European Chemicals Agency)に申請・登録しなければならない。使用を制限されるべき物質については欧州化学物質庁の承認が必要。代替がきかない物質にかぎって承認されるが、その場合でも別物質への代替化検討の計画書の提出が求められ、かつREACH-ITへの登録が必要となる。世界で初めてのITが必要不可欠な法律といわれているのはこのため。
化学物質管理は企業にとって大変な負担となる一方、管理のニーズに答えるソフトウエアやサービスを提供するIT関連企業にとっては 新たな需要を生むビジネスチャンスという側面もあります。
2008年12月1日が予備登録期限
REACH発効の2007年時点で段階的導入物質を年間1トン以上製造または輸入する業者は予備登録を行う義務があり、それ以降に段階的導入物質を新たに製造または輸入したいとする業者は、その数量が1トンを超える前に予備登録を行う必要がある。
2010年12月1日までに
年間1,000トン以上の物質や強い毒性物質などの登録が必要。
2018年6月1日までに
年間1トン以上の物質は全て登録しなければならない。