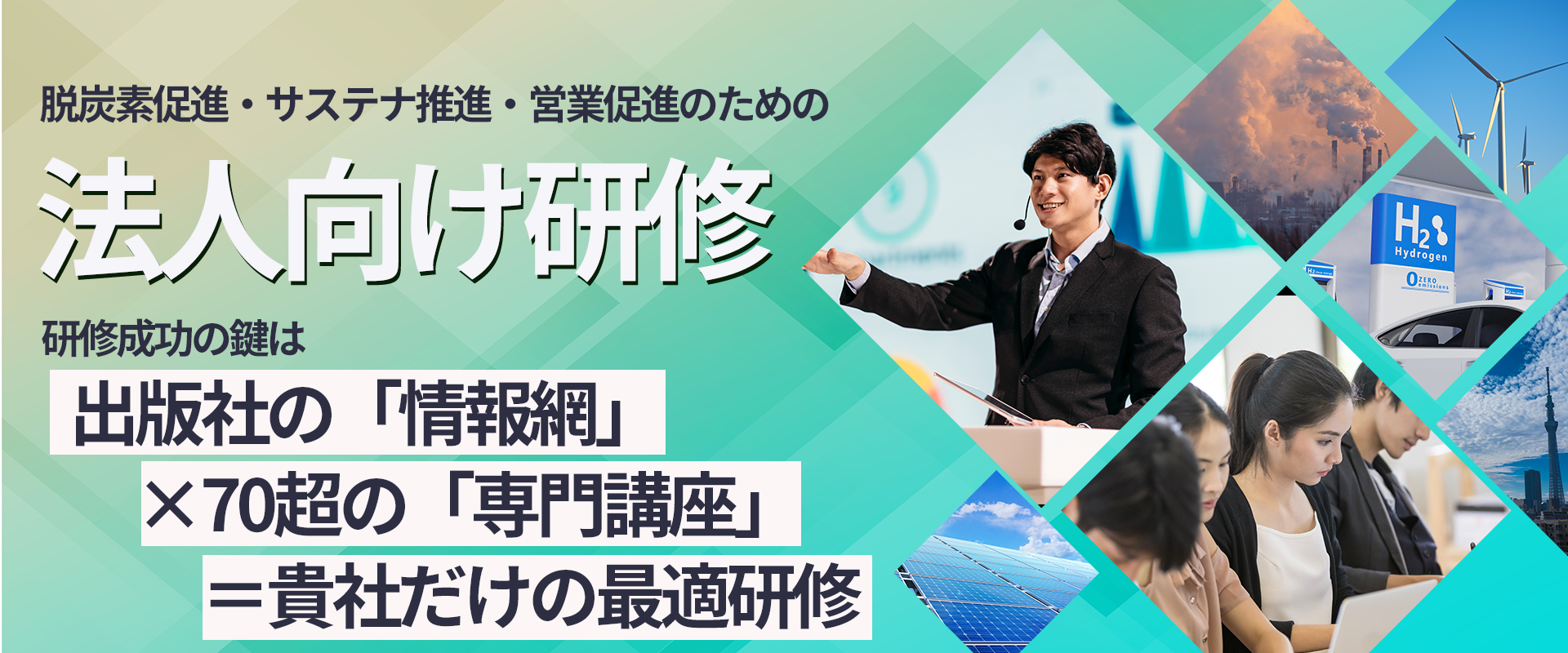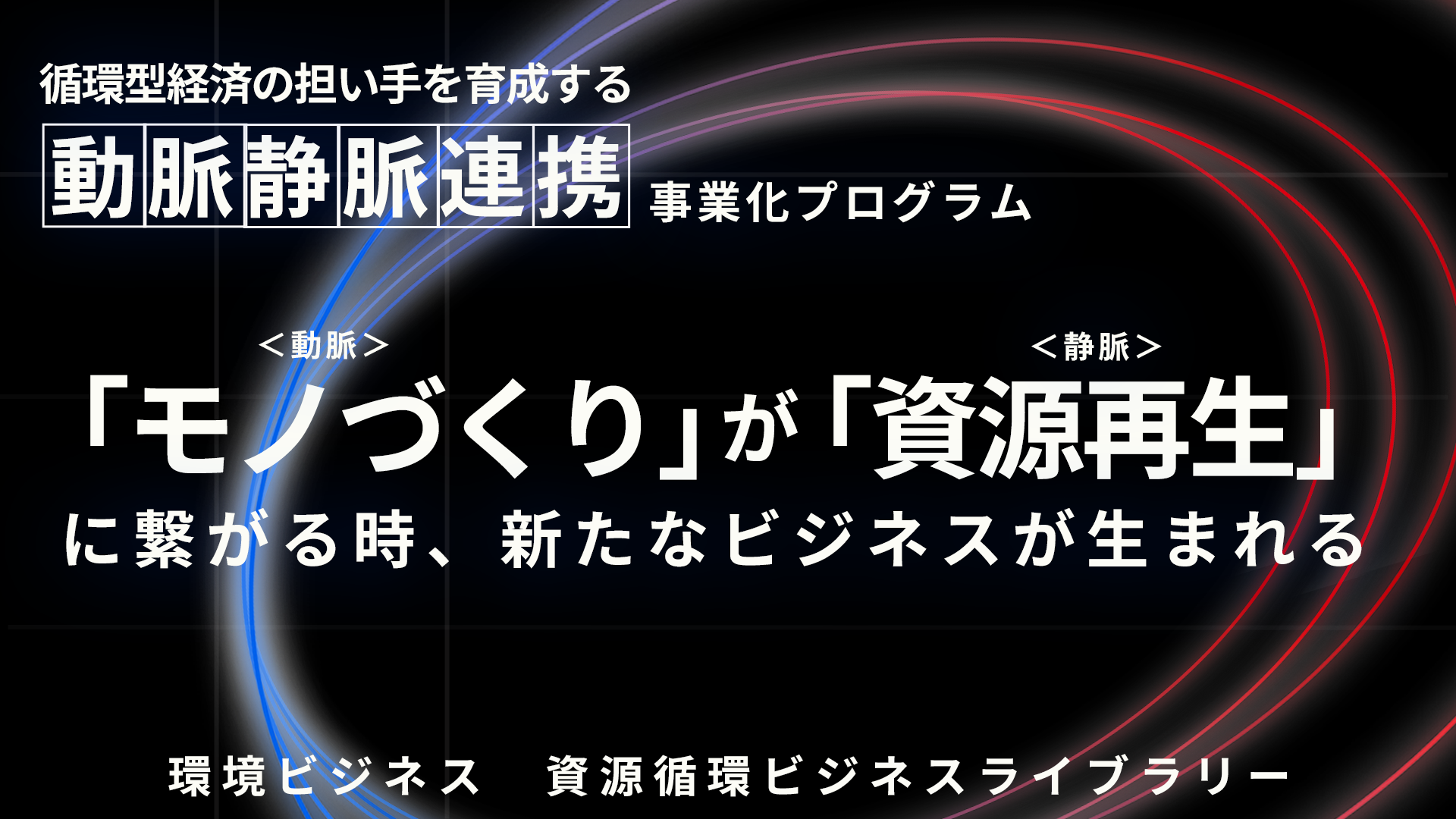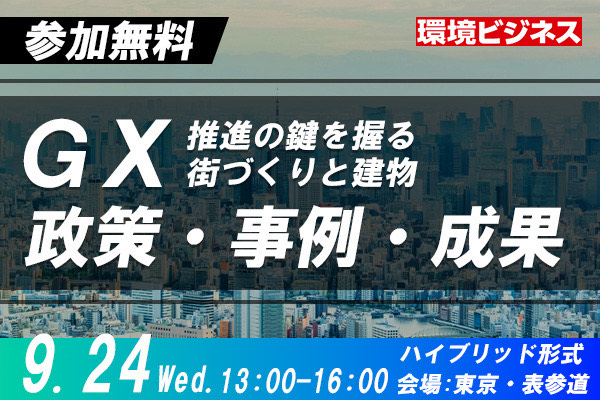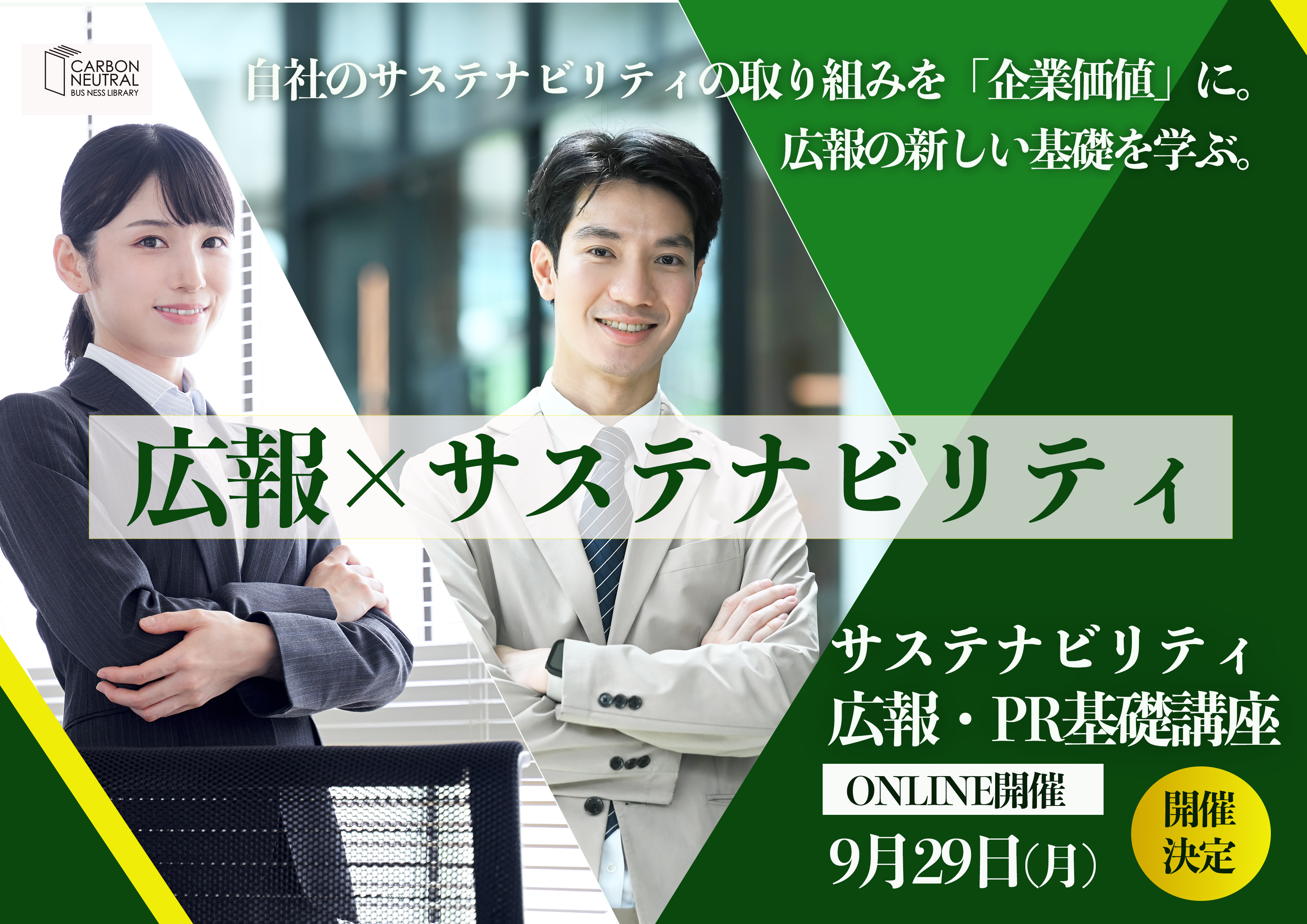環境用語集 NDC
NDC(Nationally Determined Contributions:国が決定する貢献)とは、各国が気候変動対策のために自主的に設定する温室効果ガス排出削減目標や適応策のこと。NDCは、2015年に採択されたパリ協定の枠組みに基づいており、各国が自国の状況に応じた対策を策定し、定期的に更新・強化することとされている。
次期NDCは、2025年2⽉までの国連提出が求められている。2025年はパリ協定が採択されて10年の節目にあたり、各国は2035年までの温室効果ガスの排出削減目標をNDCとして示す。
NDCの特徴
各国が自主的に決定
京都議定書とは異なり、トップダウン方式ではなく、各国が自ら目標を設定するボトムアップ方式を採用している。
グローバル・ストックテイク(GST)の実施
5年ごとに世界全体の進捗を評価し、各国がNDCを見直すための仕組み。初回のGSTは2023年に実施された。
2つの主要目標
排出削減(緩和策): 各国が削減する温室効果ガスの量や、再生可能エネルギーの導入目標など。
適応策: 気候変動の影響に適応するための対策(防災、農業・水資源管理など)。
日本におけるNDC
日本政府は、気候変動対策として策定するNDCについて、2030年までの温室効果ガス排出削減目標を2013年比で46%削減するとともに、50%削減の高みにも挑戦する方針を掲げている。
この目標達成のため、政府は再生可能エネルギーの導入拡大や、電力部門における水素・アンモニアの活用、さらには原子力発電の適切な運用を進めるとしている。
産業・運輸・家庭部門において、産業界ではカーボンリサイクル技術の活用や炭素回収・利用・貯留(CCUS)技術の導入が推進される。一方、運輸部門では電気自動車(EV)や燃料電池車(FCV)の普及の加速が重要視され、家庭・オフィス部門では高効率な電化製品の普及が進められる見込みだ。
また、NDCの実現に向けて、市場メカニズムの活用も強調されている。GXリーグの構築をはじめとする国内カーボン市場の活性化や、JCM(二国間クレジット制度)を通じた途上国との協力が、その主要な柱となる。特に、GXリーグを通じて企業が自主的に排出削減に取り組める環境を整えることで、持続可能な経済成長と脱炭素化を両立させるねらいだ。
日本政府は2023年のGSTの結果を踏まえ、2025年の更新に向け、さらなる削減目標の強化や、新技術の導入を検討している。政府は、これらの取り組みを通じて、国際的な脱炭素の流れに適応しつつ、日本独自のエネルギー政策との調和を図る方針を示している。
【参考】
- 環境省・経産省-NDC・地球温暖化対策計画の検討状況について