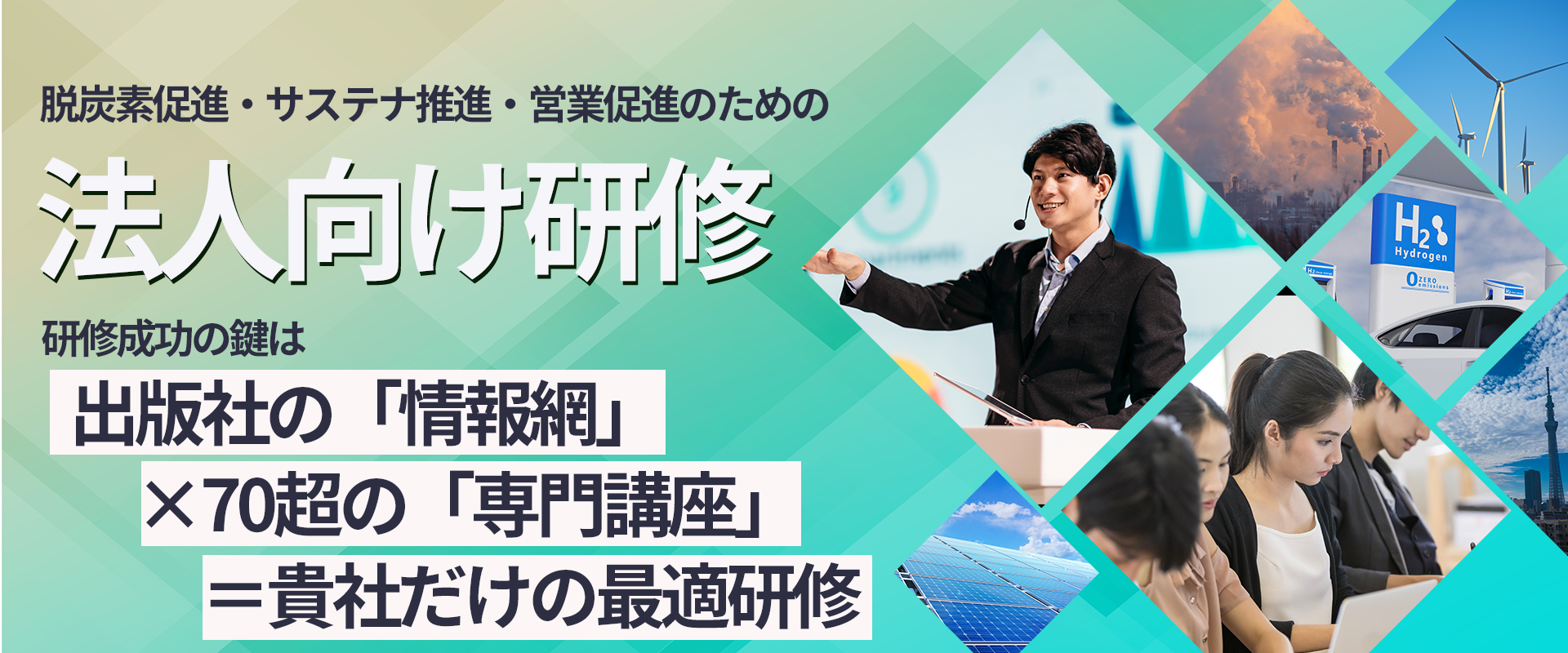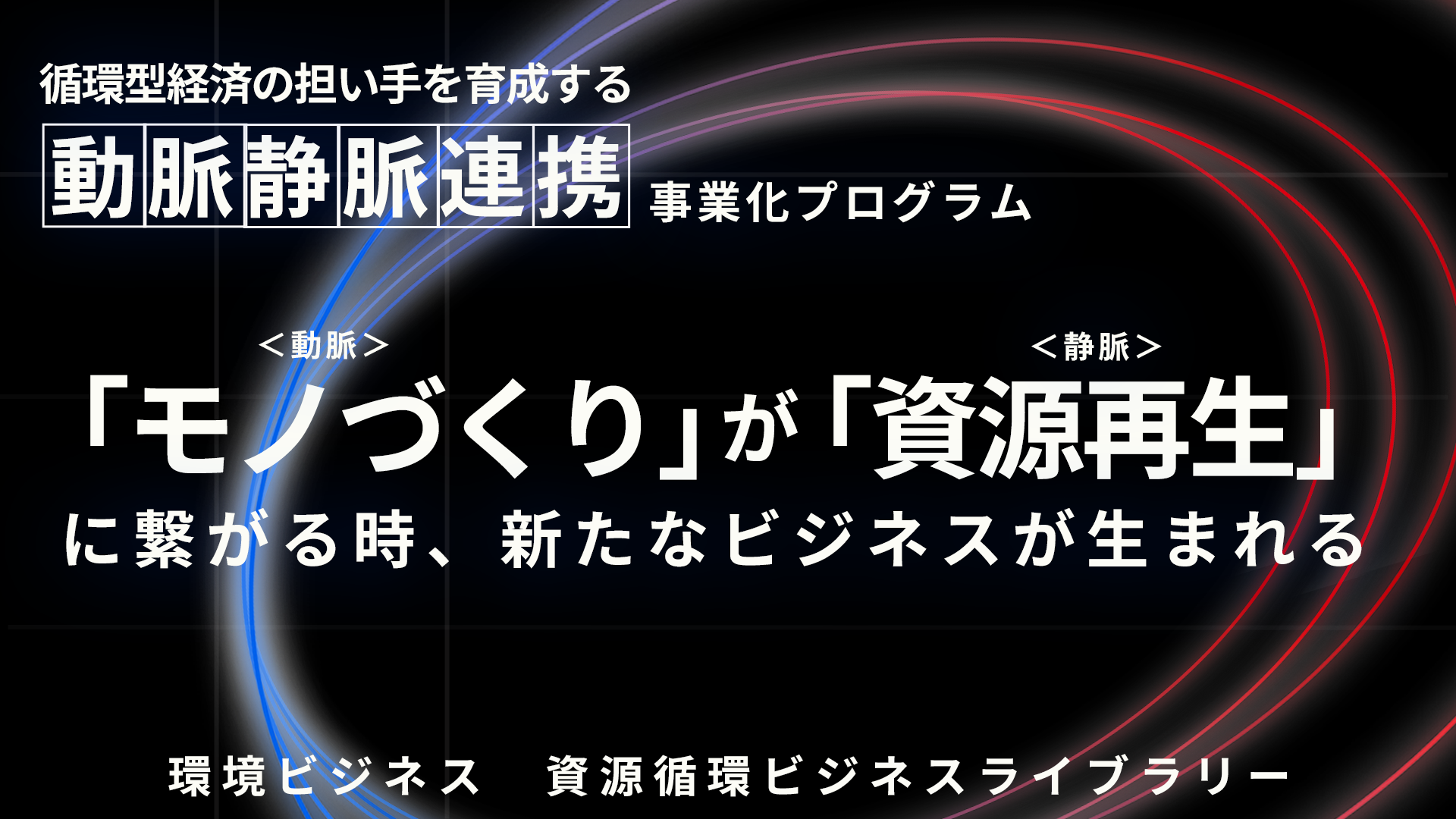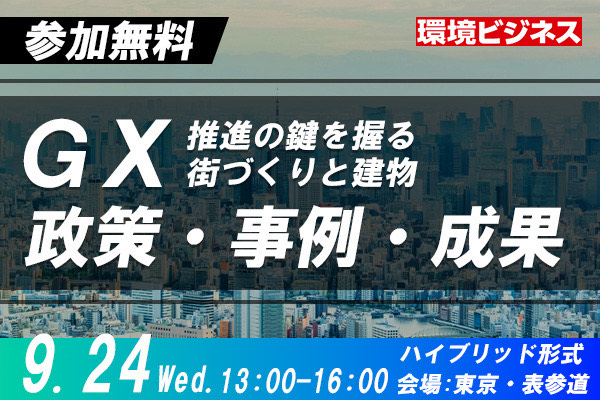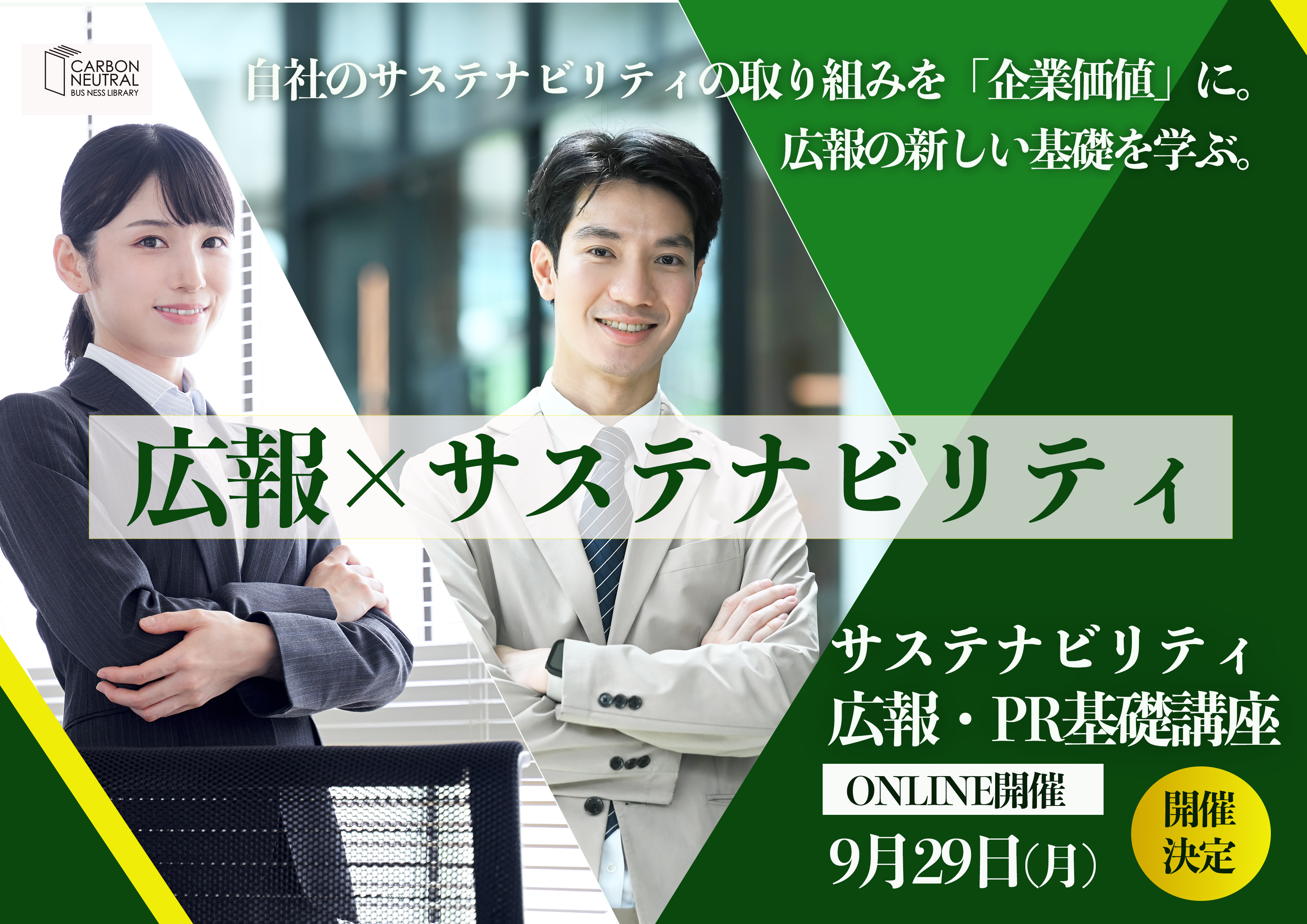環境用語集 SBT
概要
SBTは、温室効果ガス削減目標の指標のひとつ。2015年に採択されたパリ協定が求める、いわゆる『2℃目標(1.5℃目標)』が求める水準と整合した企業が中長期的に設定する温室効果ガス削減目標と、この目標が示す社会の実現に資する目標設定を促す枠組みを指す。
Science Based Targetsの略称で、直訳すると「科学と整合した目標設定」。その目標とは、パリ協定で求められる上記目標実現に向け、最新の気象科学が必要だと示す数値と整合する必要がある。
WMB(We Mean Business)の取り組みのひとつとして実施されている。世界資源研究所(WRI)、CDP等のWMB構成機関が設立運営している。
2℃目標(1.5℃目標)とは?
パリ協定で示された世界共通の長期目標。WB2℃(well-below2℃)とも記載される。
産業革命前からの気温上昇を2℃未満に抑制することを規定するとともに、1.5℃までへの抑制に向けた努力の継続に言及するもの 。
また
- 主要排出国・途上国(米国、中国、インド等)を含むすべての国が、削減目標(努力目標)を策定し国内措置を遂行
- 自国の取組状況を定期的に報告し、レビューを受け
- 世界全体としての実施状況の検討を5年ごとに行う
必要がある。
なお日本は、中期目標として、温室効果ガス(GHG)を2030年度に2013年度比26.0%削減(2005年度比25.4%減)することを目標としている。
参加要件や手続きなど
認定までの概要は、以下の通り。
- コミットメントレターを事務局に提出(任意)
2年以内にSBTを設定するという宣言 - 目標を設定
SBT事務局が発行する設定マニュアル等(SBTi基準)に準拠する。なお、この基準は段階的にバージョンアップがされており、2019年4月には、より高度な水準が求められるVer.4.0に更新されている。 - SBT認定を申請
- SBT事務局による目標の検証確認と回答
- 目標がSBTi基準を満たしていることが確認されると認定、STB等のウェブサイトにて公表
- 排出量と進捗状況を年1回報告し開示
- 定期的に目標の妥当性を確認
大きな変化などが生じた場合、必要に応じ目標の再設定が必要。なお、少なくとも5年に1度は再評価が必要
要件の概略は、以下の通り。
- 目標年
公式提出時から5年以上、15年以内の目標 - 基準年
最新のデータが得られる年で設定することを推奨 - 対象範囲
サプライチェーン排出量
目標レベルは、以下の通り。
最低でも2℃を十分に下回る水準に抑える削減目標を設定。さらに、1.5℃目標を目指すことを推奨している。具体的には、SBT事務局が認定するSBT手法(2手法)と排出シナリオ(2シナリオ)の組み合わせにより目標設定。
なお、Scopeを複数合算した目標設定が可能。ただし、Scope1+2はSBT水準を満たすことが前提。また、他者のクレジットの取得による削減、削減貢献量は、SBT達成のための削減に算入はできない。
メリットなど
SBT事務局によると、パリ協定の採択で低炭素経済への移行が世界的に加速しており、同時にあらゆるセクター、市場の変革が求められているという。この流れはイノベーションを生み出し変化を促すため、野心的な目標を設定した企業は市場の強力なプレイヤーになることもできるとしている。また、政策や規制へ備えたり、これらへの参画も期待できるとしする。
投資家、顧客、従業員、NPOなど各ステークホルダーに、パリ協定と整合する持続可能な企業であることをわかりやすく示す手段でもある。特に、SBTはCDPスコア向上にもつながるため、これにより市場からの企業評価を高めることにも寄与する。なかでも機関投資家は、中長期的なリターンを得るために企業の持続可能性を評価する傾向にあるため、ESG投資の呼び込みなどに役立つ。さらに、リスク意識の高い顧客に対し、自社のビジネス上のリスの低さを示すことで、新たな機会獲得も期待できる。
SBT認定コミット中の⽇本企業
現在、コミット中の企業は世界で1,167社(うち⽇本企業30社)。世界的には⾦融・保険・⾷料品が、⽇本では電気機器が多い。
2年以内のSBT設定をコミットしている⽇本企業30社は、次の通り。
建設業:⻄松建設
⾷料品:カゴメ/キッコーマン
繊維製品:帝⼈
化学:⼩林製薬/資⽣堂/ロックペイント
ガラス・⼟⽯製品:⽇本特殊陶業
⾮鉄⾦属:フジクラ
⾦属製品:⽂化シヤッター
機械:スミダコーポレーション/DMG森精機
電気機器:アドバンテスト/エスペック/村⽥製作所/ルネサスエレクトロニクス/ローム
輸送⽤機器:⽇⽴Astemo
その他製品:ミズノ
陸運業:佐川急便
空運業:ANAホールディングス
情報・通信業:メルカリ/ヤフー
⼩売業:セブン&アイ・ホールディングス
⾦融・保険業:MS&ADインシュアランスグループホールディングス/SOMPOホールディングス/東京海上ホールディングス
不動産業:ヒューリック
サービス業:H.U.グループホールディングス/ダイセキ
(出所:環境省)
※以下、動画(5分51秒/「脱炭素ビジネステスト」の教材として使用する動画のダイジェスト版)
【参考】
- \申込企業増加中!/ 脱炭素ビジネステストの詳細・お申し込みはこちら