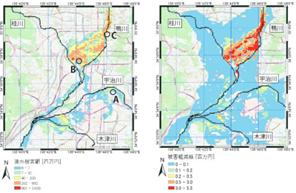水の循環について研究する「水文学(すいもんがく)」に関して、工学の観点から研究を行っている京都大学大学院工学研究科の立川康人教授。水文学は、大雨や洪水によって引き起こされる被害を防止し軽減するためにも活用されている。水文学が社会課題をどのように解決するのか、研究の醍醐味とは何か、立川教授に話を聞いた。(連載第7回、バックナンバーはこちら)
水循環のメカニズムを理解し、水害に備える
水文学とは、陸上の水循環を主な対象とする地球科学の一分野。雨が降って雨水が地上に到達すると、大半は地表面から地中に浸透し、一部は地表を流れて川に流入して海に辿り着く。また、雨水は地表面から蒸発したり樹木を通して蒸散したりして水蒸気となり、再び大気に戻っていく。
こうした水循環のメカニズムについて人間活動による水利用を含めて研究するのが、この学問だ。水循環は多くの分野に関係する大きなテーマであり、工学や林学、農学、理学といったさまざまな分野で研究が進められている。