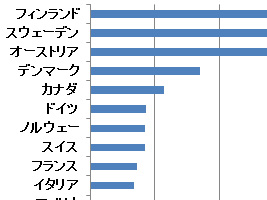われわれ人類の遠い祖先が火を使い始めたのは何百万年も前のことだが、それ以来つい最近に至るまで、木質の燃料は身近にある不可欠なエネルギー源であった。人びとは、粗朶(そだ)や薪、木炭を燃やして暖をとり、調理を行ってきたのである。この木質燃料も安価な石炭や石油が大量に出回るに及んで、完全に駆逐されたかに見えたのだが、この十数年来状況が大きく変化し、復権の兆しを見せ始めている。その背景には、化石燃料価格の根強い上昇傾向に加えて、持続可能な社会の構築を目指す国際的・国内的・地域的な取り組みがある。
わが国でも昨年から再生可能電力の固定価格買取制度が始まった。バイオマス発電への関心が急速に高まっている。今や5000kW、10,000kWの発電プラントの設立計画が全国各地で目白押しの状況だ。しかしこの出力規模では木材の持つエネルギーの20~30%しか電気に変えられない。天然ガスを使った最新鋭の火力発電所であれば60%の効率が得られるという。バイオマスがいくら頑張っても、電気だけではとても勝負にならない。
続きは有料会員登録後にお読みいただけます。
- オンラインでは実務に直結する有益なオリジナル記事を掲載
- 登録月(購入日~月末)は無料サービス
- 環境設備の導入・営業に役立つ「補助金情報検索システム」も利用可能
- 月額
- 1,300円(税込)
- 年額
- 15,600円(税込)