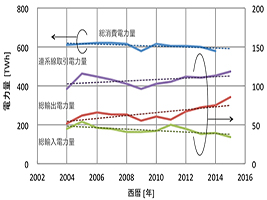これまで本コラム連載では、たびたび電力自由化や発送電分離についてさまざまな角度から取り上げてきました。いずれも共通するのは、我々は今、システム改革の只中に置かれており、改革前の「従来の考え方」をそのまま続けるのではなく、改革後の「新しい考え方」に思いを馳せないと生き残れない、ということです。
例えば、日本では「再エネのせいで系統コストがかかる」という主張は良く聞かれます。実際に再エネを大量導入するには、それなりの系統増強・拡張が必要であることは確かです。しかし、これは本来しなくてもよいのに再エネのせいで発生する無駄遣いなのでしょうか? 筆者は欧州(ときどき北米)に頻繁に出張し、欧州の送電会社(TSO)の方々からも直にお話を伺う機会も多いですが、彼らが口を揃えて言う発言は、日本とは180度異なり、「再エネのおかげで系統インフラへの投資ができる」です。同じように系統増強・拡張にお金を使うにしても、この考え方の違いは一体どこからくるのでしょうか?
続きは有料会員登録後にお読みいただけます。
- オンラインでは実務に直結する有益なオリジナル記事を掲載
- 登録月(購入日~月末)は無料サービス
- 環境設備の導入・営業に役立つ「補助金情報検索システム」も利用可能
- 月額
- 1,300円(税込)
- 年額
- 15,600円(税込)